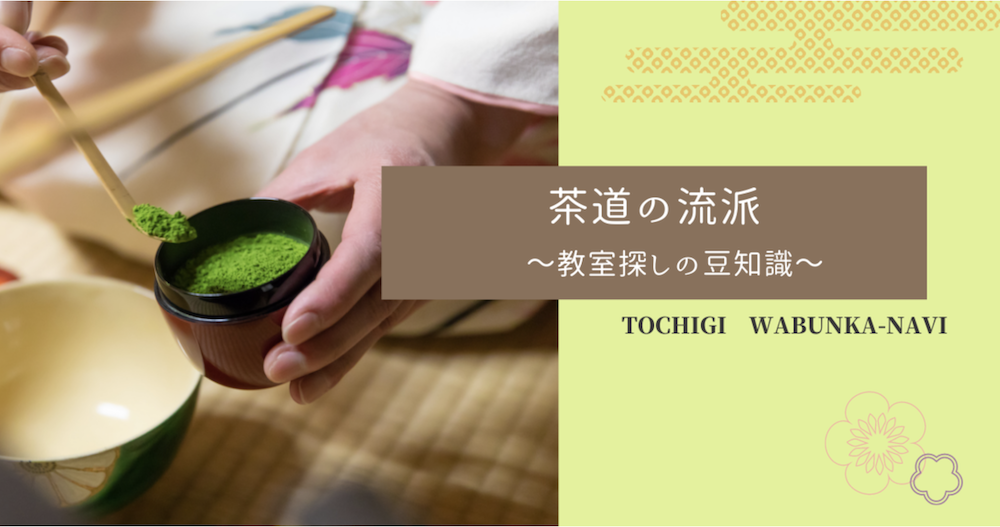はじめまして、あまのや新入社員・工藤です!
あまのやは和文化の地域振興を掲げて取り組んでいます。
その一環として、社員も和文化への知識や関心を高めたいと茶道研修を行っています。
私もそこで初めて茶道を体験しました。
人生初体験の茶道は、とても緊張しました。
でも、作法の一つひとつに相手を思いやる気持ちが込められているということを知り、覚えるのは大変でしたが、とても勉強になりました。
ただ、茶道の作法は流派によって異なるということを知り、茶道の歴史と流派について今回は少し調べてみましたので、ご紹介したいと思います!
お教室選びの参考になれば嬉しいです。
<今回の内容>
- 茶道の歴史
- 茶道の流派と作法
・表千家(おもてせんけ)
・裏千家(うらせんけ)
・武者小路千家(むしゃこうじせんけ)
- さいごに
1.茶道の歴史
茶道といえば「千利休」が有名ですよね。
しかし、茶道が日本に広まったのは千利休が生きた時代よりもはるか昔、平安時代にまで遡ります。
具体的には諸説あるようですが、一説には平安時代後期、栄西という僧が中国から茶のタネを日本に持ち帰り、北九州から京都のあたりに茶の栽培を広めたと言われています。
その後飲むだけではなく、薬として使われたり、茶の点て方や茶の味・香りから産地を推測してあてる闘茶(とうちゃ)という競技が行われたりもするようになっていったそうです。
室町時代には、村田珠光(むらたじゅこう)という僧侶が、精神性を取り入れたことから質素な茶室や茶道具を使用するようになり、亭主と客人の交流を重んじる「わび茶」を成立させました。
そして「わび茶」を発展させて「茶道」を確立したのが、有名な千利休です。
利休は茶室の造りや茶道具に深いこだわりを持ち、現代にも続く茶道の原型をつくりました。
利休亡き後は、子孫たちによって「表千家」「裏千家」「武者小路千家」という三つの流派が作られ、三千家と呼ばれる茶道の代表的な流派として現代にも続いています。
2.茶道の流派と作法
こうした長い歴史の中で、茶道の作法は流派ごとに少しずつ分かれていきました。ここでは大きな特徴をご紹介していきます。
・表千家(おもてせんけ)
古くからの作法を忠実に守っているのが特徴と言われます。
名前の由来は創設したときに受け継いだ茶室の位置。
ちょうど表通りに面していた茶室ということから「表千家」と呼ばれるようになりました。
表千家では茶道を「さどう」と呼びます。
また、作法の特徴としては、主に以下のような特徴があります。
・お茶はあまり泡立てずに抹茶の深い味が感じられるように点てる
・茶室に入るときの足は左足から入る
・礼(お辞儀をするとき)は八の字に手をつき、両手の間を少し開けて、体を30度ほど傾ける
・裏千家(うらせんけ)
時代に合わせた風潮を積極的に取り入れるのが特徴と言われます。
明治・昭和の時代に学校教育への導入などを積極的に行ったことなどから、現在においては一番大きな流派となっています。
創設時、裏通りに面した茶室を受け継いだことから「裏千家」と呼ばれ、茶道を「ちゃどう」と読むのが一般的です。
また、作法の特徴としては、主に以下のような特徴があります。
・お茶はよく泡立ててまろやかな味わいになるよう点てる
・茶室に入るときの足は右足から入る
・礼(お辞儀をするとき)は角度によって区別され、真・行・草の三種類ある
・立礼(りゅうれい)という椅子に座ってお茶をいただく方法を考案する
・武者小路千家(むしゃのこうじせんけ)
茶室を何度も消失したり、建て直しをしたりする中で、そのたびに茶室の無駄を排除し、必要のない所作を最大限省いてきたことから、無駄のない合理的な所作が特徴と言われる流派と言われます。
創設時、受け継いだ茶室が武者小路という通りにあったことから「武者小路千家」と呼ばれるようになりました。
作法の特徴としては、主に以下のような特徴があります。
・お茶はお椀を少し傾けて、あまり泡立てないように点てる
・茶室には柱側の足から入る
・礼(お辞儀をするとき)は左手が前になるように両手を合わせ、背筋を伸ばし頭を下げる
3.さいごに
いかがでしたでしょうか?
お教室選びの際には、関心のある作法のお教室をのぞいてみてもいいかもしれませんし、ご自宅から通いやすい距離にあるお教室に行ってみるなど、ご自身なりのお教室選びの軸を見つけてみるとよいかもしれませんね。
また、先生の雰囲気やお教室の様子などを知ってみたいという方は、入会前に一度見学にお邪魔させていただいたり、体験レッスンをさせていただくということもご相談してみてもよいかもしれません。
茶道のお稽古は奥が深く何年にもわたりお稽古が続いていきますので、できるだけ長く続けていけそうな環境が見つかるとよいですよね!
迷うな、ちょっと話をきいてみたいな、という方はあまのやにもどうぞご相談くださいね。
魅力の詰まった和の習いごとを一人でも多くの方に楽しんでいただけるよう、私たちあまのやは応援していきます!
はじめてお稽古にいくときの持ち物などについては、こちら「茶道の服装と持ち物|はじめてのお稽古」にまとめていますので、こちらもどうぞご覧になってくださいね!
❁❁❁ TOCHIGI 和文化ナビ ❁❁❁
日本にはこんなにステキな文化があるのに、伝えきれていないのが現状です。
実際に体験して、素晴らしい文化・地元の文化を広めていきたいと思っています!
【栃木和文化ナビ】では、「習いたい人」と「教えたい人」をつなげるプロジェクトを行っています。
和のお稽古にご興味ある方はこちらをご覧くださいませ。
栃木県小山市・栃木市・下野市・壬生町・野木町・茨城県結城市・古河市・八千代町近隣の和文化の先生をされている方で、生徒さんを募集されたいけれど、あまりインターネットなどが分からないという先生方もぜひお問合せください。
あまのやは和文化の地域振興を応援しています!